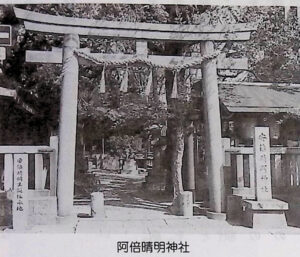西成・阿倍野歴史の回廊シリ—ズ(四)
阿倍野王子神社と晴明神社 (元町九)
十一世紀前期以来盛んになったものに、王朝貴族の四天王寺詣、住吉神社詣、高野山詣および熊野詣がある。
その中でも最も遠路を行く熊野詣は、淀川を船で下り、天満八軒屋辺りで上陸し、四天王寺、住吉、堺、泉佐野を経て田辺から山の辺の道を通り熊野本宮へ向かう、往復百七十里、約三週間のコースが一般的であった。
この熊野街道の沿道には「熊野九十九王子」と称せられている多くの神社があり、熊野詣をする人々はこれらの王子を巡拝しながら本宮へ詣でた。現大阪市域で元の位置にある王子社は安倍野王子神社のみで、他は合祀や移転させられている。
皇族の道中は農民への重税
延喜七年(九〇七)宇多上皇から始まつた熊野御幸は、弘安四年までの三百七十余年間に白河・鳥羽・崇徳・後白河・後鳥羽・後嵯峨・亀山の上皇や法皇によって百回近くも行われたが、特に後白河法皇などは三十四回、後鳥羽上皇も三十ー回という記録をつくっている。彼等の御幸は所々の王子社で供奉の公卿に和歌の詠進をさせるなど華やかでぜいたくな道中であった。
源平の争乱に加えてこれら皇族の遊興や旅行は、摂河泉の農民に重い負担をかけ、このことが頼朝の死で元気付いた後鳥羽上皇が、院政を復活して幕府を押さえようとした、承久の乱の失敗にもつながっていった。
庶民の熊野詣は幸福への悲願
庶民にとっての熊野詣は苦しくて厳しいものであった。それにもかかわらず、華厳経による補陀落浄土こそは熊野であるとして、「蟻の熊野詣」といわれる程、えんえんと行列をつくって詣でたということは、うちつづく天災、大火、疫病そして戦火を何とか逃れたいという、切なる気持ちによるものであったのだろう。
空海ゆかりの阿倍野の氏神
阿倍野の氏神として今も親しまれている王子神社は極めて古い創建であるが、天長二年(八二六)のとき全国的に疫病か流行した際、空海が一千部の薬師経を読経し、一石に一字を書写して祈ったところ疫病がやみ「痾免寺」の勅号と勅額を受けたとある。この痾免寺は当神社の神宮寺として、今も印山寺と改称しその法灯が継がれている。
阿倍野王子神社の祭神はイザナギ、イザナミ、スサノオノ、ホンダワケノ命、阿倍野王子そして男山八幡宮を合祠している。境内のくすのき三本が市
阿倍野王子神社北側に阿倍晴明神社がある。祭神は平安中期の天文博士で阿倍臣の子孫。天慶七年(九四四)に当地で誕生し、陰陽道にすぐれ天文博士、太膳太夫、左京太夫、播磨守を歴任寛弘二年(ー〇〇五)に没した。
境内に「産湯の井戸」があり、晴明の産湯を汲んだところといわれている。また「恋しくば訪ね来てみよ和泉なる、信太の森のうらみ葛の葉」で有名な葛の葉子別れの像もあり、都会の中にひとつ忘れられたような、こじんまりした静かな神社である。
塔心礎は出土の地へ
往昔、四天王寺庚申堂の巽方に、大化の改新の際左大臣に任ぜられた阿倍内倉梯磨建立の阿倍寺という広大な寺院があったという。
この寺は阿倍寺千軒といわれ極めて広大な地域を有していたらしいが、昭和十年松崎町二丁目の松長大明神の境内から古瓦(複弁八葉連華文軒丸瓦・重弧文軒平瓦)、塔心礎が出土し、その塔心礎の大きさから、相当大きな堂塔伽藍が存在したことが裏づけられ、白凰・天平時代(六四四―七九四)のものだろうと云われている。この塔心礎、現在はなぜか西成区の天下茶屋公園にあるが、貴重な大阪府指定の文化資料としても、本来のしかるべきところへ移すべきではないだろうか。
今回も、その旧跡を撮影した動画を付けました。どうぞこちらも、お楽しみください。
【注記】
ルビ(ふりがな)の表記は、ruby タグを、太字部分は、b タグを、大きいフォントでは、font タグを用いています。
本文や画像の二次使用はご遠慮ください。