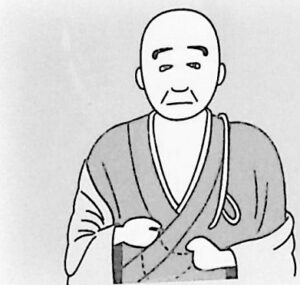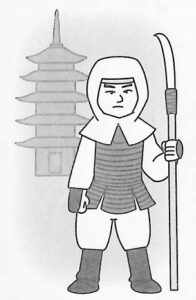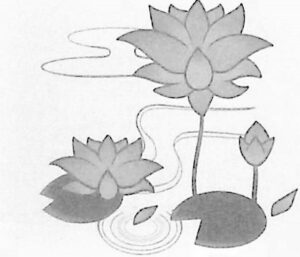がもう健さんの「西成百景」から続く「郷土史シリーズ」も手持ちの原稿はすべてアップしました。また、続編があれば、投稿予定ですが、ひとまずは終了です。長年のご愛読に感謝するとともに、2025年6月号から、連載をはじめました「照る日曇る日シリーズ」を順次掲載してゆきますので、よろしくお願いします。
今まで、溜めた雑文の中や、新しく書き起こしたものやら、「照る日曇る日」と名付け、老小児科医の繰り言を連載することにした。しばし、お付き合いをお願いする。
医者のシンボルと言えば、首にかけた聴診器が真っ先にあげるだろう。以前、ある雑誌に、その聴診器にまつわる、当方の思いを書いたが、今回は、その補足である。
一昨年まで、複数の保育園児の健診を担当していたが、昨年で、お役御免となった。その時の、エピソードから…
年長児(5-6才クラス)は、健診でのさいごの機会となる。そこで、なにかちょっとした企画をすることにしていた。やや「セクハラ」気味だが「チュー」しようか、「ハグ」しようか、と提案しても、なかなか園児の賛同が得られない。そこで、この数年来、「自分の心臓の音を聞いてみようか?」というと、診察に使っていた聴診器を自分の耳にかけたがる。子どもの手をとり、心臓の上に当ててあげる。「聞こえたかな?」「ウン、ウン」「そうだよ、自分の『心(こころ)』を聴いてるんだ。もし、将来、この中から、医師になる子が出てきたら、そういうお医者さんになるんだよ」と、そっと願ってみていた。
健診の診察票に、保護者の質問コーナーがある。そこに「将来、医師になるためには、今何をすればいいですか?」と書かれた方がおられた。「うーーん、困った、強いて言えば、仲間と、うんと遊ぶことかな?」、こんな答えでよかったかな?
写真は、病児保育室での「聴診実習」の様子。
2025年6月号搭載