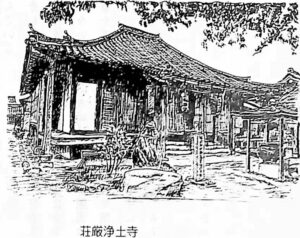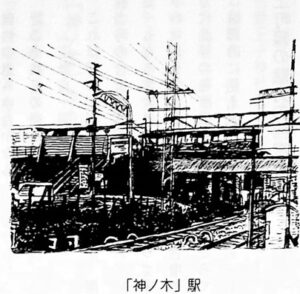◎万代池 (住吉区万代三)
熊野街道沿いに南へ、阪堺電車上町線の帝塚山三丁目駅から帝塚山四丁目駅へ行くほぼ中間の東側に、万代池がある。
今は人家が立て込んで、街道より少し東へ入ったところになっているため、見逃してしまうかもしれないから、注意が必要だ。
しかし、発見するや初めての人なら、思わず目を見張って「ほお一」とか「あれ一」と声を上げてしまうだろう。市内ではめずらしい、周囲約七百蓊の巨大な楕円形の池で、真ん中に小島もある、堂々たる風格の代物だ。
感動のない人いらっしやい
最近物事にあまり感動しなくなっている人は、ぜひとも訪れてみたらよい。後悔はしないと思う。
池の畔に等間隔で植えられた染井吉野の桜の樹が、四月の初めに一斉に開花して、やがて満開となり、春の風に花吹雪となり、歩道にピンクのじゅうたんをつくる。鏡のような池の面はその情景を忠実に逆さまに映している。市街地の中の花見では、私は文句なしにここが「日本一」だと確信する。
桜の花には何の罪もないが
しかし、万代池も池面に映る永い歴史を、さまざまな思いでみてきたのではないだろうか。池の北側の広場には、大きな「忠魂碑」がいまもある。戦中、多くの若者が、いや最後には父親までもが、この池を家族や親戚、友人たちとゆっくりと一回りして、万感の思いを胸に、あの侵略戦争に出征軍人としてかりだされていった。「桜の花のようにいさぎよく死んでこい」といわれ、かれらが 最後に仰いだ万代池の桜。池の北側に十年程前まであった、府立女子大の先輩たちもよく小旗を手に、出征の列を見送ったと聞く。
敗戦で花よりダンゴの時代
戦後、池の柵は薪として持ち去られ、桜の花も忘れて人々は、池の魚に群がつた。どじょうの化け物のような大物を釣って、みんなで食べるといっていた人は果たして無事だったのか。
しばらくして、池に貸しボートが登場した。地元の新制中学の生徒が、男女でボートに乗っていたことが大問題になり、友人たちは退学処分反対の対策を考えていたが、「厳重注意」だけで終わったということもあった。当時、流行歌では「湯の町エレジー」が大ヒットしていた。
日本の経済成長にしたがって、花見もしだいに豪華になり、カラオケのセットも業者が出張してやるようになり、池面に歌声が響き渡ったりした。
そして今は、大型開発による税金の無駄遣いで財政赤字の府は、女子大跡地をマンション用地に売り払うため、後に入っていた府立貿易専門学校を廃校にしようとしている。
古代は古墳か崖の割れ目か
古代この池には大小の古墳がひしめきあっていた。今でも近くに帝塚山古墳が市内で唯一、前方後円墳の形のまま残っている位だ。
万代池も古墳で中の小島が古墳で、池が周壕だという話もあり、小島が貧弱なのは長年の間に波に浸食されたというのだろうか。
他に、上町台地の割れ目を塞いで池にしたという説もある。
曼陀羅経で退散させた魔物
伝説として、この池には不思議な魔物が住んでいて往来の人々を苦しめるというので、聖徳太子がこの池で曼陀羅経をあげて魔物を退散させた。万代池の名前の由来はそれからきているということである。池の中央に今も、古池龍王が祀られているところをみると、魔物とはやはり龍であったのか。
万代池の「まんだ」は奈良時代の「地名は好字二字にせよ」との勅令によるものと思うが、万代はその時の当て字だと思う。もともと「まんだ」とは古地名にありアイヌ語ではないか。一体、アイヌ語で「まんだ」とは何なのか。それがわかれば、魔物の正体も判明するかも知れない。