◎弘治——伊藤村長父子の義侠
弘治小学校の校名の由来を調べてみた。西成区内に十四の小学校があるが、いずれも地名を冠した名前の学校であり、弘治小学校だけがそうでないのを不思議に思ったからである。
朝役・神役の故事
その結果、それは弘治小学校の地元である旧今宮村の歴史に深く関係しているということが判明した。旧今宮村には、永く村人が誇りとしている朝役・神役の故事があった。すなわち朝役とは朝廷に日々の魚を奉る役で、この起源は平安初期にまでさかのぼることができるという。天正の頃より戦乱のため中絶したが江戸時代に毎年の正月の行事として復活し、明治維新後まで行なわれていた。
神役とは、毎年六月の祇園會に今宮村から人数百十六人が上洛し神輿駕輿丁を奉仕するものである。かかる奉仕に対し朝廷が課役免除の恩典を与えた。その年(一五五八年)の年号が弘治でそれを冠して、弘治小学校となったのである。しかし同校はもともと今宮第一尋常小学校という由緒ある名前がついていたのである。それを昭和十六年にわざわざ変えたということはやはり、当時の国策に影響されたものであったのではないか。
守られなかった恩恵
ところが、朝廷の恩典はあくまでも紙の上でのことであり、実際は豊臣・徳川の世となっても、課役免除の実施は一向にされなかった。朝役は正月のみになったとはいえ、神役はひきつづきおこなわれており、そのために村は多大の費用を要したのである。
二百年目の勇気
天明(一七八九年)の頃、当時の村長伊藤勝右衛門はこの恩典のまったく実施されていないのに憤慨し、代官を経由し幕府に約束を守るよう請願、大いに奔走したがその後病にたおれてしまった。すると今度は隠居していた父の宇内が代わってこのことにあたり、江戸幕府に直接取り調べもされたが、主張をまげずにあくまでも恩典の実施をせまった。その後寛政年間に至り、新代官篠山十兵衛の斡旋により要求の一部が容れられるようになった。寛政八年より村高弐千百五拾余石に対し納高八百六石と定まり、その後明治維新後まで変わりなくつづいた。かりにこれを五民五公として年々弐百七拾彦石六斗三升五合の租を免除されたことになり、これもひとえに伊藤勝右衛門、宇内親子の義侠によるところである。
庶民の歴史から学ぶ
大正四年編纂された「西成郡史」には、伊藤親子のことが誇らしげにかいてあるのに、昭和四十年編纂の「西成区史」にはまったくふれられず、課役免除の恩典が続けられていたようなかきかたで歴史をゆがめている。こんな気骨のある先人のたたかいをなぜまっさつしようとするのか。行政の立場からおしきせの歴史を押しつけることはおことわりである。

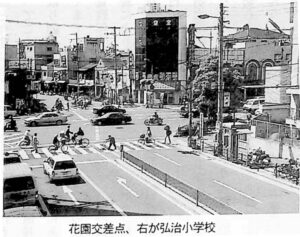
“今昔西成百景(021)” への2件の返信