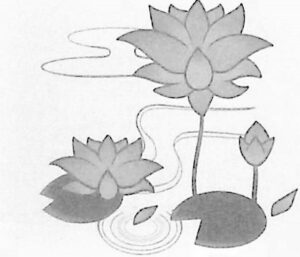◎二十七、泉涌寺の楊貴妃観音
京都駅からJR奈良線に乗って一つ目の東福寺駅から歩いて約二十分、泉涌寺への参道は総門をくぐると二つに分かれる。左が御陵参道、右が正門の大門前へ通じる。
ここは斉衡三年(八五六年)、山本左大臣緒嗣が神修上人のために開き、初めは法輪寺と称し、のち仙遊寺と改めたのがおこりとされるが、寺伝ではそれより以前に空海が建立したのを緒嗣が再興したのだという。
ついで、建保六年(一ニー八年)宇都宮信房が月輪大師に寄進し、泉涌寺と改称した。
月輪大師は十年余りの歳月を中国に渡り、修学に過ごして帰朝した、当時の代表的な学僧であった。弟子の堪海も大陸へ渡り、帰朝にさいしてさまざまな文物をもたらした。
その中でふだん拝観できるのは、大門を入った左手、観音堂に安置されている木造の観音菩薩像と羅漢像とである。観音菩薩像は唐の玄宗が美貌で名の高かった皇后楊貴妃を追慕してつくらせたとの伝説があり、楊貴妃観音の名称で親しまれている。豪華な宝冠や装身具で飾られ、あでやかな彩色をほどこしたこの像は、面長な顔立ちと妖艶ともいえるような秀麗さで、こうした伝説が生まれるのも頷ける。
また山内には、西国三十三札所第十五番目の観音寺や中世の大きな木造釈迦如来立像を本尊とする戒光寺、あるいは毎年十月中旬に行なわれる二十五菩薩お練り供養で名高い即成院がある。
今日の次郎と友子の目的地だ。
「泉涌寺は本堂に行き着くまでに、このような楊貴妃観音、本造釈迦如来立像では全国一高いという戒光寺、即成院本堂には阿弥陀如来像をかこむ二十五菩薩の群像などで、それぞれ圧倒的な浄土教の世界を体感できるのが他の寺院にない特徴だね」
目を輝かせる次郎を見て、友子が「次郎ちゃん、大感激ね」と嬉しそう。
「時間をかけて拝観することが大事だね。そうすれば極楽を体感できるよ。こんなところは他にはないよ」
友子の言う通り、次郎は感激した様子だ。
友子も頷いて「『地獄極楽この世にござる』と云うのだから、何もお金を払って地獄を見にいく必要はないと思う。見るなら極楽、泉涌寺前だね」と同意した。
極楽気分の次郎はいつも以上に明るい声で「友ちゃん、今日はタクシーで京都駅まで飛ばして、一杯飲んで帰ろうか」と友子を誘った。
少し間を置いて、次郎は「ホツトコーヒーをね」とお茶目に付け足した。
そんな次郎に友子が「認知症のお兄さんと同居して介護している次郎ちやんは、極楽間違いなしよ」と励ます。
「そんなこと云つてくれるのは友ちやんだけや」
感激する次郎に「みんな見てくれてはるよ」と友子が優しく続けた。
今日の次郎は極楽帰りと友子の言葉のおかげで、いつも以上に機嫌が良く饒舌になっていた。
「『日常が何よりも大切で愛しい』という言葉が好きやから、何かあったら兄を抱いてやる、ハグやね」
「お兄さんは…?」と友子が恐る恐る聞くと、次郎は明るい声で「抱き返してくれるよ」と答えた。
「今日は何かうれしいね」と二人で笑った。
極楽気分でホツトコーヒー。