◎庚申街道
四天王寺南門から南へ、庚申堂に沿う道は庚申街道と云われているが、明治三十一年に命名されたものでそう古くはない。庚申堂付近は道路も広く、両側の商店のたたずまいから、街道の面影も残っているが、それから南へは右や左に曲がつており、本来は平野や長吉に至る道だが、最近ではこのあたりを庚申街道と知る人も少ない。
正善院は全国庚申の総本山
庚申堂は俗称で正式には正善院と云い、諸国庚申の本寺であり、明治までは、地方で庚申を祀るにはこの寺の免許を得る必要があった。
お寺の由来書によれば、「文武天皇の頃、全国に悪疫流行し多くの被害をだした。四天王寺の民部僧都豪範という大徳がこれをなげき、この地に草庵を結んでひたすら祈願したところ、大宝元年(七〇 ー) 正月七日夜、青衣総角の一童子が現われ『われ帝釈天の使いなり』と青面金剛童子の像を授けた。豪範がその霊像を諸氏に礼拝させると、悪疫たちまち終息したので、みんなはよろこんで豪範を当寺の開山とした。霊像を授かった日が庚申だったところから、六十日毎にくる庚申の日には参拝客で賑わうが、毎年正月の初庚申には殊の外雑踏する」と書かれている。
大空襲により堂宇全焼したが、 昭和四十七年(一九七二)に万国博の印度館を移築してようやく本堂を再建、中に四天王等を安置している。
土塔山超願寺で見たものは
庚申堂から四天王寺南門までのんびりと歩いていると、西角に土塔山超願寺という古いお寺の墓地があった。浄瑠璃の名匠竹本義太夫誕生地でお墓もある、との石碑があったので、無人の墓地にそっと入っていった。
通告板下げた無縁墓の隊列
しかし、私は、竹本義太夫の墓を探す前に、その場で不思議な光景に出くわして、足を止めてしまった。
お墓には入口から、高さ二㍍位の立派な墓石が続いていて、さすが天王寺のお金持ちのお墓という感じが先ずした。しかし不審に思ったのは、それらの墓石のほとんどに白いブラスチックの板がぶら下げられていたことである。ちかず<ママ づ?>いてみると、その板には、「このお墓にお参りの方は必ずお寺に立ち寄ってください。お届けのない場合は無縁の処置をとらせていただきます」と書いてある。
これら板を掛けられている墓に共通することは、いずれも昭和十二・三年に中国北部で戦死し、勲章をもらっているニ十歳代前半の兵士のものだということである。側面に経過が細かく刻まれているが、銃弾を受けながら尚も敵兵を刺殺したというのもある。
おそらく、結婚前の故人等には当然子孫はなく、親兄弟も絶えてしまい、詣る人もなくつ いに無縁仏になってしまったのであろう。下げられていた板は、墓を処分するというお寺の最後通告なのである。
それにしてもその数のなんと多いこと、私には声無き声が聞こえたような気がした。
庚申の夜を眠れない人々
庚申の夜は眠らず明かす守り庚申の俗信が、平安朝の貴族社会に広がり、徹夜で詩歌管弦を催す「庚申御遊」の宴が開かれ、中世の武家社会では、これが「庚申講」とも云われた。江戸時代に入ると民間でも行われ「お長い話は庚申の晩に」など云われるようになった。
土塔山超願寺にお墓を立てた親兄弟は、庚申の夜をどう過ごしたのであろうか。

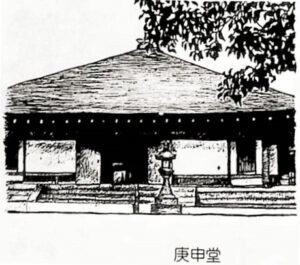
“今昔木津川物語(041)” への1件の返信