◎ あとがき
あとがき
人は人生の岐路に立たされたときに、一体何をしなければならないのか。それは、足元を見直してみることだと云われている。この場合もちろん、自分の置かれている立場という意味もあるが、私はあえて、現に住んでいるところ、いま立っている場所を問題にしたい。これなら「見解の相違」ということも起きる心配はないのではないか。
「まあこれが終のすみかか雪五尺」一茶。の、心境からの出発だ。そうすると、全く何も知らないことに気が付き、がくぜんとする。私もそうだった。悩んでいるどころではない。自分の存在すら、確認し直さなければならないのだ。
頼りにしていた、大正時代発行の「西成郡史」を開いてぴっくり。今の西成区のことはほんの少ししか載っていない。ほとんど西大阪地域のことである。図書館から借りた「西成区史」には、在り来たりの名所・旧跡の案内ぱかり。しかしその中から、「殿下茶屋」が「天下茶屋」になった、という説明に疑問を持つ,ちょうどその時「天下茶屋史跡公園」抹殺の現場にぶっかり、 大阪市や区役所の「好きやねん西成」キャンペーンのええかげんさ、矛盾がだんだん見えてくる。逆に私の中にやる気がわいてきて、のめりこむきっかけになったという次第である。
私は史料万能主義者でなない。庶民の立場から大胆に仮説を立てて、史料で裏付けをとっていくやり方をしている。不明な部分は、私の我流の推理としてすすめていく。「逆説古代史」に対して、私のは「逆説郷土史」である。意識していなくても、自然とそうなっていく。それほど今の「公認郷土史」が歪められているのである。
私は約十年前から「郷土史」を書き出している。木津川沿岸の西成・住之江・大正・西・浪速区とそれらの区に隣接する、住吉・阿倍野・天王寺・港区を対象としている。もちろん昔は、こんなに細かく区分されていなかったからである。私の場合、この郷土史探究の活動が、幾度かの人生の岐路を乗り切るのに大いに役立ったと思う。今も心を癒してくれている。もちろん、宗教色はいっさいなしにである。何故かといえば、やはりこの地で、かって「生きて、悩んで、かくたたかった人がいた」という事実が実感として味わえて、それに少しでも自分が新しい光を当てることが出来たという、誇りと喜びを持てたということではないだろうか。
そして今で五十七回になる毎月一回の、「木津川史跡めぐり三時間の旅」で知り合った多くの素晴らしい仲間たちとの交流がある。この喜びを一人でも多くの人に知ってもらい、川の流れが自然に豐かなものになっていくように、郷土史研究の今後を展望してこの度、「今昔(こんじやく)木津川物語」(ご家庭保存版)を発行した。
二〇〇三年七月
が も う 健
参考文献 大阪府史・大阪市史・西成・住之江・大正・西・浪速・住吉・阿倍野・天王寺・港区史・大阪史跡事典
【編者注】
これで、『今昔木津川物語』のアップロードは、最終になります。引き続き、『次郎と友子の「びっくり史跡巡り」日記』 をお楽しみください。

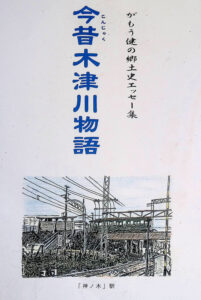
“今昔木津川物語(058)” への1件の返信