
◎石清水八幡宮と「荒城の月」
京阪八幡市駅前の道を南に約三分歩くと、今日の行先である石(いわ)清水八幡宮の一の鳥居に到着する。
駅前から登山ケーブルが運行されているので、高齢者の二人には大いに助かる。
由来にはこうある。
「石清水八幡宮は男山(一四二メートル)の頂、鳩ケ峰から谷を挟んだ東尾根に座し、山全体が境内である。応神天皇・神功皇后・比咩大神の三柱をまつり、官幣大社であった。都の裏鬼門である西南を守護し、伊勢神宮につぐ国家第:の宗廟、国家鎮護の神として崇敬されてきた」
「社伝によれば、ハ五九年(貞観元年)に奈良大安寺の僧行教が豊前の宇佐八幡宮で神託を受け、清和天皇の命により神殿六棟を男山に造営し、実権は行教の出身氏族紀氏が握らこととなった。明治維新まで僧による神前読経が行なわれ、神仏混淆の当時にあってもきわめて仏教色の強い神社であった。江戸幕府の庇護により江戸中期には四十を超える坊舎が立ち並び、壮観な宗教景観を有していたが、一八六八年(明治元年)の神仏分離令により残っていた二十三坊全て廃絶し、山内景観は一変した」と。
由来を見て、友子が反応する。
「灯が消えてしまった。明治維新政府のやつた事なのね」
次郎が答える。
「日本に仏教が入ってきた時には神道との争いがあったが、背景は政治の問題なので、奈良時代には仏教信仰と固むの神祇信仰信とを融合調和する神仏混淆説か唱えられ、仏菩薩がけ日本では仮に神の姿で現われる。阿弥陀如来は.八幡神、大日如来は伊勢大神と考えられるようになった。しかし、江戸時代国学の隆盛につれ、仏教的要素を神道から除き、神道の優位性を強調する運動が激しくなり、 ついに明治維新には排仏希釈<ママ 廃仏毀釈?>まで進んだのだ」
友子が驚く。
「打ち壊しのことね」
次郎が続ける。
「一八六八年(明治元年)ー」)]の神仏判然令により、神官・平田派国学者らを中心に、神仏分離、神社における仏堂・仏像・仏具などの破壊や除去が各地で行われた。これに対して、排仏反対の民衆の動きや、信教自由の主張が高まり、その後信教自由の保護が各宗に通達された。しかし、この運動により政府は政治優先の思想を普及させることができ、その後の侵略戦争に宗教界を全面的に駆り出すことができるようになった」
友子は「恐ろしい歴史があるのね。だから政治と宗教の分離は絶対に必要なのね」と納得した。
次郎が頷く。
「この男山を登るといつも『荒城の月』が歌えてくる。なにか落城的な感じが…」
友子が驚きつつ言う。
「神社内には『エジソン記念碑』があって、トーマス・エジソンが男山付近で採取された真竹でフィラメントをつくり白熱電球を完成させたことを記念してー九三四年(昭和九年)に造立されたと、びっくりね」
「今日も勉強になったわ」と一日の感想を話していた友子だが、やはり最後は次郎の介護について思い遣った。
お兄さん、認知症の進行はあるの?
次郎が答える。
「夜間不穏症状が出ているのか、夕方から不機嫌になる傾向が最近よく見られるんだ」
友子は心配そうに「疲れがたまってくるのではないの?」と返した。
「それもあると思うけど…」
少し暗くなった次郎に、友子が明るく言う
「次郎ちゃんは夜間陽気症状で対抗して!」
次郎は友子のジョークに笑いながら「それはもともとあるので…」と答えた。
今日も明るい表情で、手を振る二人であった。
・大阪きづがわ医療福祉生協機関誌「みらい」 2020年12月号 大阪きづがわ医療福祉生協機関誌「みらい」 2021年1月号収録


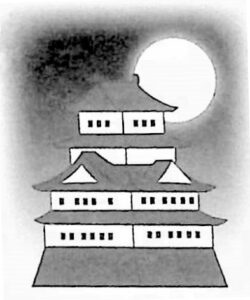
“がもう健の〉次郎と友子の「びっくり史跡巡り」日記 第54回、第55回” への1件の返信