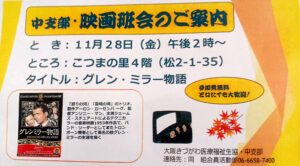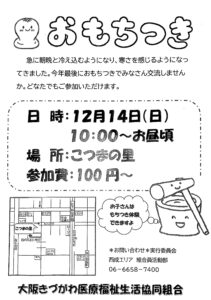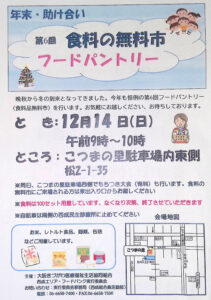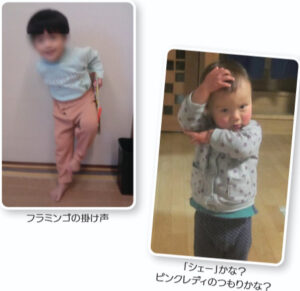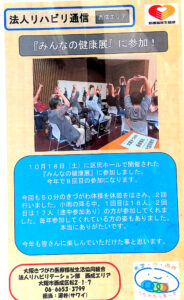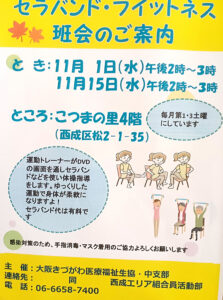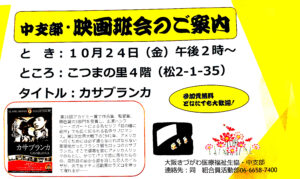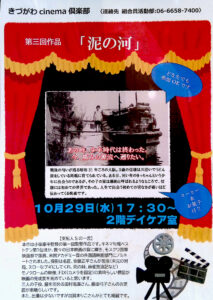今年は、太平洋戦争から84年、先々月に終了した朝のNHKドラマ「あんぱん」では、出征する主人公嵩の「壮行会」が放映された。今まで息子をあまり顧みなかった松嶋菜々子演ずる母親の「生きて帰ってきて!」という叫びがあるのが見せ場であった。そこで、なぜその場面が印象的なのかを、やや「理屈」っぽく(笑)考えてみた。
ドイツの劇作家ブレヒトが提唱した演劇理論に「異化効果」というのがあるが、まさにこれに当たるだろう。くわしい語句の説明は、AIくんに、お任せするが、学生時代に拙いながら芝居つくりにいそしんだ身で、自分勝手に少し芝居のセリフを整理すると、
1)まともな人がまともなことを言う
2)まともでない人がまともでないことを言う
3)まともな人がまともでないことを言う
4)まともでない人がまともなことを言う
の場合、観客が「なるほど」と理解が深まるのは、1)から4)の順で高くなる。今回の母親の訴えは、4)に該当する。突然東京から高知へ現れた非現実感は無視されても、である。過去の母親の否定的な演技表現は、その伏線であったのだ。加えて、のぶの夫が出航前につぶやく「日本は、この戦争に勝てるとは思わない」は、1)にあたり、普通なら面白くもなんとないのだが、この場合は「異化」を、より効果的にしているのは心憎いほどだ。「反戦作品」として世評が高かったのは肯けよう。
余談だが、診療所での診察では、大部分は1)で終始するが、ごくたまに、2)から4)のシーンに遭遇しないとは限らない。少々の「猜疑心」を抱きながら(苦笑)、患者さんの話を聞くとは、つくづく因果な商売である、
やなせたかしは、戦後の高知新聞記者時代、日本共産党の代議士、山原健二郎とも交流があり、大逆事件で冤罪となった人たちのインタビュー記事を書いた。「戦争はいやだ」とする原点は、戦時中から一生涯変わらなかったのだ。
2025年12月号搭載