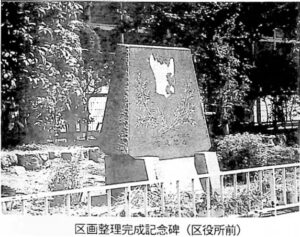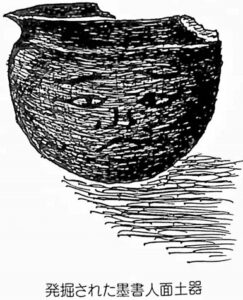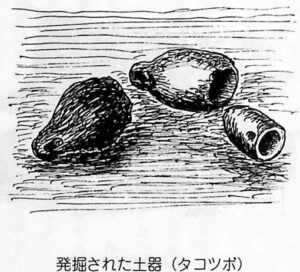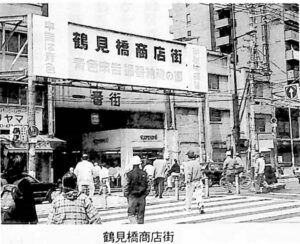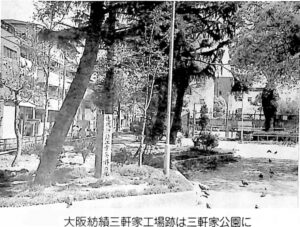西成区で火事でもあれば新聞やテレビは必ずといってよいほど、「住宅密集地で」と報道する。西成といえば緑の少ない、道のせまい、乱開発の典型のようにみられているふしもある。
しかし例えば、潮路二丁目五番地にある西成民主診療所の前から北を望めば、道が一直線に伸びて、約二千メ—トル先の浪速区の丁芦原橋駅前辺りまで見通せるということを、知っている西成区民は案外少ないのではないだろうか。
他からきた人の方が区内中央部で街路が碁盤の目のようになっているのをみて「まるで小京都だ」とおどろくのである。
事実北から北開・中開・南開・出城・長橋・鶴見橋北・鶴見橋・旭北・旭南・梅・梅南・松・橘・桜・柳という十五の東西の通りと八つの南北の筋がそれぞれ等間隔で交差している。
三十年間で八百人が九万四千四百人に
この地域は旧今宮村にあたり、北は関西線、南はほぼ柳通り、東はほほ紀州街道、西は十三間掘川(現阪神高速道路)に接し、明治三十年の新たに村が形成されたときには、人家はわずかに紀州街道付近に百七十戸あるていど、人口は八百内外であった。面積こそ玉出町に比してやや大きなものはあるが、村役場さえ単独で維持できないー寒村にしか過ぎなかったのである。それが三十年後の大正十三年十月一日には人口が百十倍以上の九万四千四百人と、全国的にも比類のない激増により全国第三位の大きな町となっていた。この間大正六年には町政を敷き今宮町と改称していた。
俘虜収容所が耕地整理のきっかけに
明治三十七、八年の今宮村には未だ耕地とならない広大な地域があり、小松がまばらに生えた平野となつていた。そこへ当時日露戦役において必要となった口シアの俘虜収容所がつくられることになった。六千人余を収容する敷地六万坪の巨大施設であった。これはその後一時、陸軍第十六師団の仮営舎にあてられたが明治四一年には全部返還された。しかしそのときには各地主の前の境界が全く判明されず、これを旧に復することはきわめて困難な状態となっていた。そこで時の村長勝田愼太郎氏は将来の発展のために耕地整理を断行することを決意。同年十一月発起人会を発足させ、四三年より工事に着工し大正九年まで十年の歳月をかけて完成させた。同時に幅二間ないし三間の整理した道路もできたが、最初は田畑や荒地の間に区画されただけで、雨ともなれば泥だらけで歩行にも困難をきたすものであったという。尚、今宮の耕地整理は大阪市内では初めてのもの。
勝田村長らの功績は偉大
この事業は字地域の変更や地番の整理はもちろんさまざまな苦心と多額の経費を要したが、勝田村長等は第一期工事をなすにあたり寝食を忘れて熱中したと伝えられている。この先人たちの英断と努力によって、その後の人口の急増による地域の乱開発が奇跡的にまぬがれたのである。耕地整理は現在の区画整理。
勝田氏は一期で村長の職を退き、晩年は不幸にして不遇な境遇に終わったというが、この地における功績は実に偉大であったと記録されている。
西成へなにわ筋が延伸
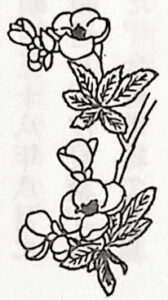 さて今度この地域を二分する形で、北から南へ幅員二十五メ—トルの道路が千二百メ—トルにわたり建設されることになった。終戦直後に都市計画された加島天下茶屋線(なにわ筋)の西成区内への延伸計画が約五十年ぶりに実施されるはこびとなったのである。今年から八年間で用地買収がなされ、その後二年間で道路が完成するという。長橋から南へ柳通りをこえて南海汐見橋線に接し、あとは道路に沿って新開通りまで進んで終点となる。
さて今度この地域を二分する形で、北から南へ幅員二十五メ—トルの道路が千二百メ—トルにわたり建設されることになった。終戦直後に都市計画された加島天下茶屋線(なにわ筋)の西成区内への延伸計画が約五十年ぶりに実施されるはこびとなったのである。今年から八年間で用地買収がなされ、その後二年間で道路が完成するという。長橋から南へ柳通りをこえて南海汐見橋線に接し、あとは道路に沿って新開通りまで進んで終点となる。
立退を要求される世帯約一千。今までは大きな車も入ってこず、夜間の通行もまばらという静かな環境が今後は大変な交通公害に悩まされることになり、市の計画のままでは、便利さを差し引きしても、事態は深刻である。先人の英知に学びつつ、住民の立場にたった西成の街づくりも、これからいよいよ正念場をむかえる。